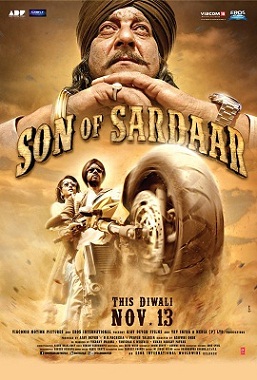
スィク教徒はインド全人口の2%ほどに過ぎないが、ヒンディー語映画を観ているとそのプレゼンスの強さを感じる。例えばヒンディー語映画の中でスィク教徒のキャラクターがコミックロールを担うことが多い。先日公開されたばかりの「Student of the Year」(2012年/邦題:スチューデント・オブ・ザ・イヤー 狙え!No.1!!)はその典型例であった。これは、インディアンジョークの中でスィク教徒(サルダールジー)が主人公になることが多いのと関係しているだろう。しかし、それだけでなく、「Gadar: Ek Prem Katha」(2001年)、「Jo Bole So Nihaal」(2005年)、「Singh Is Kinng」(2008年)など、ターバンを頭に巻いた典型的なスィク教徒を主人公に据えた映画がコンスタントに作られ続けており、とても2%の存在感とは思えない。
実はヒンディー語映画界にはパンジャービーが多い。スィク教の本拠地であるパンジャーブ地方では、ヒンドゥー教とスィク教が共存関係を築いて来ただけあって、ヒンドゥー教徒であってもスィク教を同時に信仰していることは少なくない。また、1947年の印パ分離独立時にパーキスターン領となったパンジャーブ地方から逃げて来た難民たちも、ヒンディー語映画界に多く流入している。そんなこともあって、スィク教は映画界の中で愛される存在となっており、スィク教徒が主人公の映画も時々企画に上がるのだろう。アジャイ・デーヴガンの新作「Son of Sardaar」も、その題名から察せられる通り、コテコテのスィク教徒が主人公の映画である。
毎年ディーワーリーは大予算型の期待作が数本公開され、まるで映画祭のような状態になるのだが、今年のディーワーリーはヤシュ・チョープラーの遺作「Jab Tak Hai Jaan」(2012年)と、アジャイ・デーヴガン主演「Son of Sardaar」の一騎打ちとなった。監督は「Atithi Tum Kab Jaoge?」(2010年)をヒットさせたアシュウィニー・ディール。まだ3作目であり、経験は浅い。だが、前作はとても軽妙なコメディー映画で、信頼できない名前ではない。ヒロインはソーナークシー・スィナー。まだデビューから間もないのだが、いい作品に恵まれており、勢いがある。他にサンジャイ・ダット、ジューヒー・チャーウラー、カメオ出演のサルマーン・カーンなど、豪華なキャストだ。十分期待作といっていい。ちなみに、この映画はテルグ語映画「Maryada Ramanna」(2010年/邦題:あなたがいてこそ)のリメイクである。
監督:アシュウィニー・ディール
制作:アジャイ・デーヴガン、NRパッチースィヤー、プラヴィーン・タルレージャー
音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー、サージド・ワージド、サンディープ・チャウター
歌詞:サミール、アンジャーン、シャッビール・アハマド、マノージ・ヤーダヴ
振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ
出演:アジャイ・デーヴガン、サンジャイ・ダット、ジューヒー・チャーウラー、ソーナークシー・スィナー、プニート・イッサール、ムクル・デーヴ、ヴィンドゥー・ダーラー・スィン、アルジャン・バージワー、タヌジャー、ラージェーシュ・ヴィヴェーク、サルマーン・カーン(特別出演)
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサントクンジで鑑賞。
ロンドン在住のインド人スィク教徒ジャッスィー(アジャイ・デーヴガン)は、亡き父親の土地を売却するために故郷パグワーラーに帰る。ジャッスィーは帰国前に、自分の家族にまつわる復讐劇を聞かされていた。パグワーラーではジャッスィーの属するランダーワー家はサンドゥー家と復讐合戦を繰り広げたことがあり、その中でジャッスィーの父親は殺され、現サンドゥー家の当主ビッルー(サンジャイ・ダット)の叔父も殺されていた。そのとき結婚直前だったビッルーは、ランダーワー家の最後の末裔を殺すまでは結婚しないと誓う。だが、ジャッスィーは母親に連れられて英国に逃げていた。以後25年間、ビッルーは許嫁パンミー(ジューヒー・チャーウラー)と結婚せずにランダーワー家の末裔を捜し回っていたのである。ジャッスィーは、さっさと土地を売って立ち去れば、そんな因縁の復讐劇などとは関係ないと楽天的に考えていた。 ジャッスィーはデリーからパグワーラーへ向かう列車の中で、スク(ソーナークシー・スィナー)という美しいパンジャービー女性と出会い、一目惚れしてしまう。しかし、後に分かったことだが、スクはビッルーの姪であった。また、パグワーラーに着いてからジャッスィーが出会ったトニー(ムクル・デーヴ)はビッルーの甥であった。トニーはジャッスィーこそがランダーワー家の最後の末裔であることを知り、ビッルーにそれを報告しに行く。ところがそのときまでにジャッスィーはサンドゥー家の客として家で歓待を受けていた。 サンドゥー家の伝統では、お客様は神様であった。たとえ先代からの仇敵であっても、その伝統を曲げることはできなかった。ジャッスィーが仇相手であることを知ったビッルーは、彼がサンドゥー家の中にいる間は決して手出しをしないように部下たちに命令する。もちろん、家を一歩出たら、そのときに復讐する積もりであった。ところが、ジャッスィーもビッルーたちが仇敵であり、自分を殺そうとしていることを知る。家の中にいる内は殺されないことも知り、何とか言い訳をして家を出ないようにする。 一方、そんなことも知らないスクは、ジャッスィーが家を出たがらないのは自分に恋しているからだと考える。スクもジャッスィーのことが気になっていた。スクにはボビーという幼馴染みがおり、大の仲良しだったが、お互いに結婚する気はなかった。ボビーもスクの恋心を感じ取り、二人の仲を影ながら応援する。 ジャッスィーは一旦外に出ることになり、ビッルーやその2人の甥トニー、ティットゥー(ヴィンドゥー・ダーラー・スィン)から攻撃を受けるが、戦っている内にまたサンドゥー家の中に入ってしまい、振り出しに戻ってしまった。またジャッスィーはサンドゥー家の客として生きながらえることになった。 ちょうどローリー祭の時期であった。それに際して、パンミーはボビーとスクの婚約式を行うことを提案する。スクの本心を知っていたボビーはそれを断るが、覚悟を決めていたジャッスィーはボビーを説得し、スクとの結婚を承諾させる。ボビーとスクの婚約式は外にグルドワーラー(スィク教寺院)で行われることになった。ジャッスィーもそれに出席するため外に出なくてはならない。ボビーとスクを見送った後、外に出たジャッスィーはトニーやティットゥーたちと戦う。 一方、スクは婚約式の場で初めてジャッスィーがランダーワー家の末裔であることを知らされる。スクはボビーに説得され、婚約式を投げ出してジャッスィーの元へと向かう。ジャッスィーはスクと共に悪漢たちをなぎ倒し、ビッルーと対決しに行く。ジャッスィーとビッルーは死闘を繰り広げるが、祖母のベーベー(タヌジャー)やスクになだめられ、最終的にはビッルーはジャッスィーとスクの結婚を認めて、サンドゥー家とランダーワー家の復讐合戦に終止符を打つ。
ジャンルでいえばアクション・コメディー映画に分類されるだろうが、アクションもコメディーもお粗末だった。ロマンスは二次的な扱いであったが、やはり弱い。スケールも意外に小さく、金が掛かっていないように見えた。総じて、期待外れの作品であった。アシュウィニー・ディール監督には荷が重い内容の映画だったのではなかろうか?
基本的にアクションが売りの映画なので、ストーリーがいい加減でもアクションシーンさえ良ければ爽快感は得られるものだ。しかし、「Son of Sardaar」のアクションは奇妙奇天烈な動きが多く、素人っぽさ全開だった。改めて、「Golmaal」シリーズのローヒト・シェッティー監督のうまさが際立った。単純なように見えて、アクションシーンを撮るにもやっぱり才能が要るのである。
コメディーも外しまくりだった。多少は笑えるシーンがあるが、大爆笑とまではいかない。間が悪いのだ。ジャッスィーがサンドゥー家からなかなか出ようとしないシーンなどは間延びし過ぎてワースト・シーンだといえる。
ジャッスィーとスクのロマンスも全く感情移入できない。ジャッスィーがスクのことをどう思っているのか、それを暗示するシーンがほとんど存在しない。とにかくジャッスィーはビッルーから逃げることで精一杯で、恋愛なんてしてられなかったのではなかろうか?スクとボビーの関係も謎であるし、ロマンス部分はどれも取って付けたような展開だった。
オリジナルのテルグ語映画の影響であろうか、歌と踊りの入り方も唐突なことが多く、ヒンディー語映画の文法に従っていない。冒頭などはいきなりタイトルソング「Son of Sardaar」となり、ロンドンの象徴である時計台ビッグベンの針にアジャイ・デーヴガンが立っているところから始まる。全く訳が分からない。
こんな完成度の低い映画をよくディーワーリーにぶつける気になったなと、その勇気にだけは感心する。それだけの作品である。「Atithi Tum Kab Jaoge?」も客がなかなか帰らず苦労する話だったが、それとの共通点は偶然であろうか?
アジャイ・デーヴガンは「Singham」(2011年)でハードコアなアクションヒーローとしての売り出しを成功させ、今回はサルマーン・カーンが持ち味とするコミカルなアクションヒーローを目指したと思われる。パンジャービー家系のアジャイ・デーヴガンはスィク教徒ファッションが似合っており、彼が演じたジャッスィーは取って付けたような感じではなかった。元々コミックロールもよく演じて来ているので、アクションとコメディーをうまく一人の役の中で融合させられていたと思う。
ソーナークシー・スィナーも自信に満ちた演技をしていた。地方単館で受けそうな顔と身体をしているので、地方でより受けそうな「Son of Sardaar」のような映画への出演はいいチョイスだ。ソーナークシーの快進撃は、彼女自身の才能よりも出演作に恵まれただけだと考えているのだが、もし自分の長所をよく把握してチョイスしているのだったら、大した女優だ。
サンジャイ・ダットは「Agneepath」(2012年)に続き悪役出演。見た目に似合わず器用な俳優で、どんな役でもそつなくこなす。特に筋肉派の役はうまく、今回演じたビッルーも適役であった。
他にジューヒー・チャーウラーの出演が特筆すべきだ。一時代を築き上げた人気女優であるが、既に一線を退き、年に数本の映画に出演するのみだ。久し振りに彼女のキュートな演技を見られた気がする。
音楽は基本的にヒメーシュ・レーシャミヤー。一時期ほどではないにしても、最近活動を再び活発化させている。ヒメーシュらしい曲作りはだいぶ鳴りを潜め、映画の雰囲気に合う曲を作っている。「Son of Sardaar」の音楽は悪くない。
言語はパンジャービー語混じりのヒンディー語。変則的なヒンディー語となるので、ヒンディー語のみの知識だと聴き取りに苦労するだろう。
映画の舞台となっているパグワーラー(Phagwara)は実在の地名で、パンジャーブ州カプールタラー県の町だ。カプールタラーやパグワーラーには行ったことがないが、おそらく実際にカプールタラー県各地でロケが行われていたのではないかと思う。
「Son of Sardaar」は、ディーワーリー公開の期待作であったが、対抗馬の「Jab Tak Hai Jaan」とは比べるのもおこがましい完成度の低いアクション・コメディー映画である。無理に観る必要はない。今は素直に傑作「Jab Tak Hai Jaan」を観るべきである。
