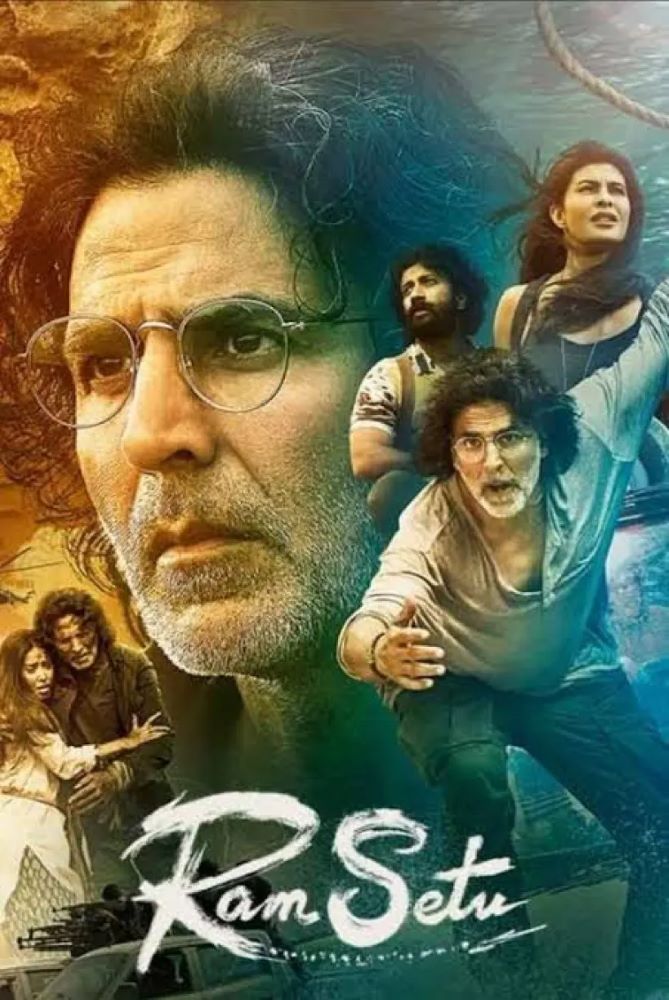
インド南部タミル・ナードゥ州とスリランカの間には、「アダムス・ブリッジ(アダムの橋)」または「ラーム・セートゥ(ラーマの橋)」と呼ばれる細い浅瀬が連なっている。スリランカといえば、「ラーマーヤナ」の中で羅刹王ラーヴァナの支配するランカー島だと考えられており、スィーター姫をラーヴァナにさらわれたラーマ王子は、猿の軍団などの助けを借りてランカー島まで浮き石を使って橋を架け、攻め入ったとされている。「ラーマーヤナ」を単なる神話ではなく歴史だと考えるヒンドゥー教徒たちは、ラーム・セートゥをラーマ王子の時代に造られた人工物だと信じ、神聖視している。
しかしながら、このラーム・セートゥがあるおかげで、インドとスリランカの間を船舶が航行することができず、遠回りをしないといけなくなっている。インドとスリランカの間の海底を掘削し、船舶が航行できる道を造ろうとする「セートゥサムドラム船舶用運河計画」は100年以上前からあるのだが、計画が持ち上がるたびにヒンドゥー教徒たちの宗教感情を刺激して激しい反対が起き、ほとんど進展していない。
2022年10月25日公開の「Ram Setu」は、このラーム・セートゥ問題を取り上げたユニークな映画だ。2014年から中央の政権を握るインド人民党(BJP)はヒンドゥー教至上主義を掲げており、ヒンドゥー教に関する事柄は現在のインドでは微妙である。もし「ラーム・セートゥは自然物である」とか「ラーマ王子は実在しない」といった主張を発信する映画だったとしたら大変な騒ぎになっただろうが、蓋を開けてみたら、「ラーム・セートゥは人工物」という結論を軸にストーリーが作られており、BJPの意向に沿う形になっている。
監督はアビシェーク・シャルマー。「Tere Bin Laden」(2010年)などのコメディー映画が得意な監督だが、過去には核実験を扱ったシリアスな映画「Parmanu: The Story of Pokhran」(2018年)も撮っており、おそらくその実績を買われてこの映画の監督に選ばれたのだと思われる。
主演はアクシャイ・クマール。彼は、モーディー政権時代に成功させた火星探査を取り上げた「Mission Mangal」(2019年/邦題:ミッション・マンガル 崖っぷちチームの火星打上げ計画)や、ヒンドゥー教徒の英雄プリトヴィーラージが主人公の時代劇映画「Samrat Prithviraj」(2022年)など、BJP寄りの映画に好んで出演している。今回彼が演じるのは考古学者である。
ヒロインはジャクリーン・フェルナンデスとヌスラト・バルチャー。他に、テルグ語映画界で活躍するサティヤ・デーヴ、南インド映画界を代表する名優ナーサル、プラヴェーシュ・ラーナーなどが出演している。
プロデューサー陣にも注目したい。「Ram Setu」は、アクシャイ・クマールのプロダクションであるケープ・オブ・グッド・フィルム、タミル語映画界の大手プロダクションであるライカ・プロダクション、そして大手OTTプラットフォームであるアマゾン・プライムビデオが共同でプロデュースした作品である。ヒンディー語映画界のプロダクションと南インド映画界のプロダクションが共同で映画を作るという現象は、昨今の「汎インド映画」的な動きといえるし、アマゾンが初めてヒンディー語映画をプロデュースするというのも画期的な出来事だ。
ちなみに、「Ram Setu」の中では、プシュカル・バトナーガルが天文学的に算出し、自著「Dating The Era of Lord Ram」(2004年)の中で主張したラーマ王子の生年月日「紀元前5114年1月10日」が採用されている。
2007年、インド政府は海運会社の社長インドラカーント(ナーサル)と協力し、ラーム・セートゥを破壊して船舶航行用運河を建造しようとしていたが、激しい反対運動も起きており、最高裁判所で係争中だった。考古学者のアーリヤン・クルシュレーシュタ(アクシャイ・クマール)は科学しか信じない無神論者であり、インドラカーントに雇われ、ラーム・セートゥが自然物であるという証拠を見つける計画を率いることになる。もしラーマ王子が実在し、その生年が紀元前5114年だとしたら、ラーム・セートゥがそれ以前から存在していたことを示せばよかった。 アーリヤンのチームには、サンドラ・レベロ(ジャクリーン・フェルナンデス)やガブリエルなどの有能な科学者がいた。また、バリ(プラヴェーシュ・ラーナー)がプロジェクトマネージャーを務めていた。アーリヤンは初期の潜水調査において、ラーム・セートゥは少なくとも1万8千年以上前から存在すると考察する。この結果はインドラカーントにとって好都合なもので、それを証拠として裁判所に提出しようとするが、アーリヤンはさらに証拠を集めるため調査を進める。その中でアーリヤン、サンドラ、ガブリエルの三人は、浮き石や珊瑚礁などを調査し、やはりラーム・セートゥは人工物であり、7千年前に建造された可能性が高いと結論づける。インドラカーントはバリに命じて三人を殺そうとするが、彼らは脱出し、スリランカ人のアンジャネヤン・プシュパクマーラン、通称AP(サティヤ・デーヴ)に助けられる。 アーリヤンたちはスリランカに逃亡するが、バリが彼らを殺すために追い掛けてきた。逃げる途中でガブリエルが殺されてしまう。アーリヤン、サンドラ、APは、タミル人ゲリラに助けられ、そこからラーヴァナ実在の証拠を探しに旅に出る。そしてラーヴァナ関連の史跡を巡る内に、ラーマ王子が実在したように、ラーヴァナも実在したという確かな証拠を得る。 バリは、アーリヤンの妻ガーヤトリー(ヌスラト・バルチャー)を人質に取るが、アーリヤンの反撃によって負傷する。また、APはヘリコプターから落ちて死んでしまう。アーリヤンはAPのバッグの中から、失ったはずの浮き石を見つける。 アーリヤンは証拠をデリーに持ち帰り、最高裁判所に提出する。裁判長は政府に対し、ラーマ王子が実在しなかった科学的証拠を提出するまでラーム・セートゥの破壊を認めない判決を出す。
2022年上半期には、カシュミーリー・パンディトの大移動を主題にした「The Kashmir Files」(2022年)が話題になった。BJPはカシュミーリー・パンディトを票田としており、この映画は親BJPのプロパガンダ映画との批判を受けたが、興行的には大ヒットした。
それと同様にこの「Ram Setu」も非常にプロパガンダ臭のする映画だ。映画の舞台になっているのは2007年だが、このとき中央政府で与党だったのは、BJPのライバルである国民会議派(INC)である。そのINC政権が、ヒンドゥー教徒たちが神聖視するラーム・セートゥを破壊しようとしているというのが物語の発端になっており、まずはINCを貶める内容になっている。
さらに、ラーマ王子の実在を疑う主人公の考古学者アーリヤンが、調査を進める中で考えを変え、科学的証拠からラーマ王子は実在し、ラーム・セートゥは人工的に建造されたと主張するようになる。また、映画の最後で出される最高裁判所の判決も、神話上のキャラクターであるはずのラーマ王子が実在した可能性を支持する内容であり、ヒンドゥー教徒のセンチメントに迎合している。極めつけは、ラーマ王子の忠実な部下、猿の将軍ハヌマーンの化身と受け止められるキャラ、APが登場している。これが親BJPのプロパガンダ映画でないとしても、時の政権にすり寄った映画との誹りは免れない。
これでストーリーや映像が良ければ、まだフィクション映画として割り切って楽しめたのだが、残念ながらどちらも一定のレベルに達していなかった。ストーリーに関しては子供だましとしか言いようがない。考古学者が主人公の割には考古学が全く掘り下げられていなかったし、ラーム・セートゥが主題の映画かと思いきや、なぜか途中からラーヴァナ探究に目的が変わる。映像も稚拙だった。ラーム・セートゥは海底に存在するため、その調査のためにアーリヤンが潜水するシーンがあるのだが、その映像があまりに拙かった。水の表現では「アバター ウェイ・オブ・ウォーター」(2022年)が新次元の映像体験を打ち出そうとしている中、「Ram Setu」では一昔前のコント劇のような映像しか提供できておらず、米国映画との技術力の差をまざまざと見せつけられてしまっていた。
アクシャイ・クマールはいつも通りのアクシャイ・クマールであった。可もなく不可もなくといったところだ。ヒロインの二人はどちらも添え物感が強く、これといった出番もなかった。APを演じたサティヤ・デーヴは躍動感があって良かった。
ラーム・セートゥやスリランカのシーンは実際にスリランカで撮影を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大により中止され、代わりにダマン&ディーウでロケが行われたようである。また、冒頭にバーミヤンのシーンがあったが、これも実際にアフガーニスターンで撮影が行われているわけではないようである。
「Ram Setu」は、ラーマ王子が建造したとされるラーム・セートゥを巡る、本来なら微妙な映画である。ただ、あまりにストーリーが幼稚だったため、真剣に受け止める必要がない。また、与党BJPに迎合して、かなりBJP寄りのストーリーになっていた。そういう忖度が入ると映画は途端につまらなくなる。興行的にも期待ほどの盛り上がりがなく、製作費は回収できなかった。今年の話題作の一本だったが、近年のヒンディー語映画不振からなかなか脱却できず、この映画も沈むことになった。
