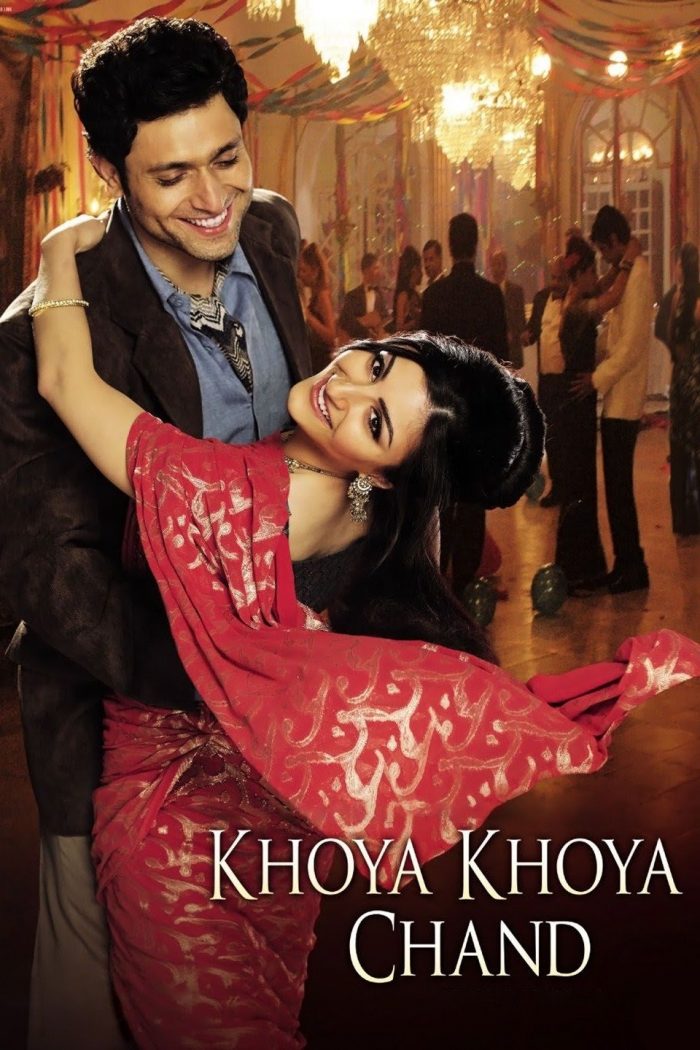
本日(2007年12月7日)より2本の新作ヒンディー語映画が公開された。まずは「Khoya Khoya Chand」を観た。題名は「失われた月」という意味である。
監督:スディール・ミシュラー
制作:プラカーシュ・ジャー
音楽:シャンタヌ・モイトラ
作詞:スワーナーンド・キルキレー
衣裳:アシーマー・ベーラープルカル、ニハーリカー・カーン
出演:シャイニー・アーフージャー、ソーハー・アリー・カーン、ラジャト・カプール、ソーニヤー・ジャハーン、ヴィナイ・パータク、スシュミター・ムカルジー、サウラブ・シュクラーなど
備考:PVRアヌパム4で鑑賞。
1950年代のヒンディー語映画界。駆け出しの女優ニカト(ソーハー・アリー・カーン)は、大スター、プレーム・クマール(ラジャト・カプール)に見初められ、あっという間にスターダムを駆け上る。ニカトは撮影中に、ラクナウーからボンベイにやって来たウルドゥー語作家ザファル(シャイニー・アーフージャー)と出会う。ザファルもプレームに気に入られ、映画の原作や脚本を担当して行く中で、業界内で有名になって行く。ニカトはプレームに恋していたが、プレームは別の女性との婚約を発表する。プレームは結婚してもニカトのことだけを愛していると語るが、次第にニカトの心は不安定になって行く。そんな中、ザファルとニカトの中は急接近し、プレームに隠れて付き合うようになる。ある日プレームにもそのことが知れてしまい、ザファルは映画業界を去ろうとするが、権力のあるプロデューサーから認められていたザファルはそのまま映画の仕事を続けられることになる。 ザファルの夢は、自分の作品を自分で監督して映画にすることだった。そして、ニカトをそのヒロインにしようとしていたが、家族の問題などでニカトと仲違いし、彼はニカトのライバルであるラタンバーラー(ソーニヤー・ジャハーン)をヒロインに抜擢する。だが、その映画は全くの失敗作に終わってしまった。一方、ニカトはプレームとの共演作に出演する。ザファルは嫉妬し、自暴自棄になる。やがてボンベイにいられなくなったザファルは、誰にも何も告げずにどこかへ去ってしまう。 それから数年の月日が過ぎ去り、1965年になった。ロンドンに移り住んでいたザファルは久し振りにボンベイへ戻って来る。彼は再び映画を監督しようとしていた。だが、映画界は彼のいた頃とはだいぶ様変わりしていた。白黒映画は消え、カラー映画の時代となっていた。ニカトも変わってしまっていた。アルコール依存症となり、スキャンダルの女王となったニカトは、銀幕から遠ざかり、ザファルの親友シャーマル(ヴィナイ・パータク)の家に住んでいた。ただ、二人は結婚をしていなかった。ザファルはニカトに出演を依頼し、彼女も承諾する。 だが、ニカトは心臓に病気を抱えていた。ニカトは撮影中に倒れてしまったが、何とか復帰し、撮影を終わらす。また、その中でニカトはザファルにプロポーズをする。映画完成から1年後、ニカトは死んでしまうが、彼女の最後の映画は後々まで語り継がれる名作となった。
いったい何を言いたいのか全く訳の分からない映画。2007年公開の映画の中ではダントツに意味不明でつまらない映画なので、観るだけ時間の無駄である。
1950年代~60年代のヒンディー語映画業界が舞台になっているということで、先月公開されたばかりの「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)を彷彿とさせた。「Om Shanti Om」の前半の時代設定は1977年だった。その部分はコメディー色・パロディー色が強かったので、多少辻褄が合わなくても受け入れることができたが、「Khoya Khoya Chand」はシリアスな映画であり、時代考証の正確さはさらに重要になる。ビンテージカーの使用や当時流行した衣装の再現によって、当時の雰囲気を醸し出そうとする努力は感じられた。また、ヒロインのソーハー・アリー・カーンの母親シャルミラー・タゴールは60年代以降に活躍した女優であり、彼女によく似たソーハーが当時のヒンディー語映画を再現するのは適役に思えた。だが、「Parineeta」(2005年)で描写されたカルカッタと同様に、美化し過ぎの部分が多々見られ、必ずしも当時のヒンディー語映画界の再現が成功していたとは言えなかった。
ヴィジュアル面の欠点はあまり深く踏み込まないでおく。「Khoya Khoya Chand」の最大の欠点は、何と言っても脚本と編集にある。誰が何を考えているのか、何が起こっているのか、なぜこういう運びになるのか、映画中でははっきりと説明されないことが多すぎる。プレームがなぜ突然婚約を発表したのかも分からないし、ニカトが女優を目指すようになった経緯もよく分からない。ザファルとニカトの破局の原因もよく分からないし、ザファルがロンドンからボンベイへなぜ帰って来たのかも分からない。シャーマルがストーリーの語り手のように登場するシーンが数ヶ所あるが、それが一貫している訳でもない。終わり方も観客を突き放している。いきなり「1年後にニカトは死んだ」などと字幕が出て、そのままスタッフロールである。そして輪を掛けて映画を意味不明にしているのが、展開の過剰な早さである。観客が流れを理解するよりも早いスピードでストーリーが展開して行くので、仕舞いには何が何だか分からなくなる。この台詞を聞き逃したらもう付いていけない、というものが多かったのもとても気になった。
「Khoya Khoya Chand」を監督したスディール・ミシュラーは、「Calcutta Mail」(2003年)、「Hazaaron Khwaishein Aisi」(2003年)、「Chameli」(2003年)などの監督である。「Hazaaron Khwaishein Aisi」は非常に高い評価を得ているが、もしかしたら実力はそれほど高くない人なのかもしれない。「Khoya Khoya Chand」は、金を出して観るレベルのものとは思えなかった。
シャイニー・アーフージャーは現在ヒンディー語映画界で活躍する若手の男優の中では最も演技力がある有望株だ。怒りと悲しみが入り混じった表情や、シニカルな笑みを浮かべた表情がとてもいい。彼は「Hazaaron Khwaishein Aisi」でデビューしたこともあり、スディール・ミシュラー監督は恩人のようなものだ。全く破綻していた映画の中で、彼の演技力だけは光っていた。
ヒロインのソーハー・アリー・カーンは難ありである。彼女は役に入り込むことが苦手なのではないかと思う。「Rang De Basanti」(2006年)のように、自然体で演じられる役が似合っている。「Khoya Khoya Chand」のような、演技力を要する役は今のところ荷が重過ぎる。カッタク・ダンスを練習したようだが、踊りにも魅力を感じなかった。
ラジャト・カプール、ヴィナイ・パータクなど、脇役陣はいい演技をしていた。ラタンバーラーを演じたソーニヤー・ジャハーンは、印パ分離独立前後に活躍した伝説的女優ヌール・ジャハーンの孫娘で、「Taj Mahal: En Eternal Love Story」(2005年)にムムターズ・マハル役で出演していたパーキスターン人女優である。
音楽はシャーンタヌ・モーイトラー。「Parineeta」に似た雰囲気の音楽が多かった。50年代~60年代のヒンディー語映画界というより、当時のハリウッドと言った感じの音楽ばかりである。
時代を反映してか、出演者にはウルドゥー語の発音練習が課せられたらしい。若手ウルドゥー語作家ザファルを演じたシャイニー・アーフージャーは特にウルドゥー語の正確な発音を要求されたようだ。
「Khoya Khoya Chand」は、今年最もつまらない映画のひとつなので、観ない方が吉だ。二度と夜空に姿を現さない月となるだろう。
