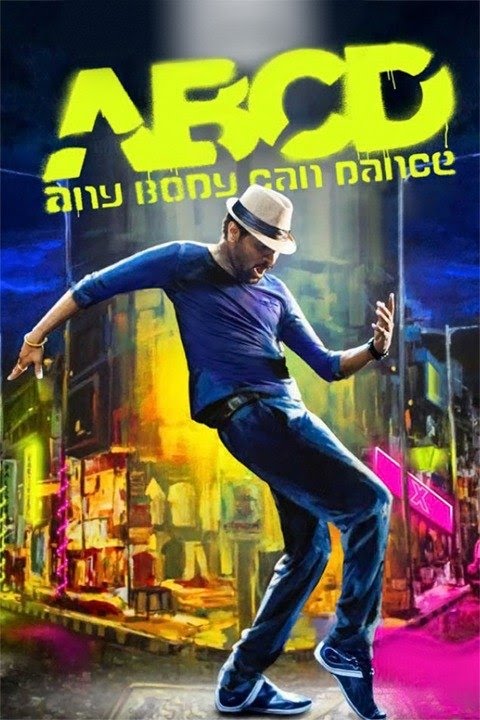
日本へ帰国する前にインドの映画館で観ておきたいヒンディー語映画を挙げて行ったら枚挙に暇がない。特に映画の予告編を見てしまうと、どれも観てみたくなってしまう。その中でも是非最後に観ておきたかった映画が、2013年2月8日公開、インド初の3Dダンス映画と銘打った「ABCD: Any Body Can Dance」であった。「インドのマイケル・ジャクソン」と呼ばれる伝説的なコレオグラファー、プラブデーヴァーが主演し、これまたコレオグラファー出身の映画監督レモ・デスーザが監督をしており、ダンスの質は予告編だけを見ても圧倒的であった。インドでも3D映画が作られるようになって久しいが、いまいち3D技術を活かした作品が出て来ていない。だが、もしインド映画が得意とするダンスを、3Dのフォーマットでより迫力のあるものに進化できたら、それは大きな業績となる。既に英米の映画界では「Step Up 3D」(2010年)や「StreetDance 3D」(2010年)など、3Dダンス映画は作られているのであるが、インド人がこの新技術をどう料理するか、見てみたかった。
主演は前述の通りプラブデーヴァーで、やはりコレオグラファーのガネーシュ・アーチャーリヤが脇役出演している。だが、物語の中心的役割を果たすのは若手ダンサーたちで、彼らの多くはインドのダンスコンペティション番組「Dance India Dance」の参加者のようである。また、ヒロインの一人は米国のダンスコンペティション番組「So You Think You Can Dance」の勝者ローレン・ゴットリーブが演じている。
監督:レモ・デスーザ
制作:スィッダールト・ロイ・カプール
音楽:サチン・ジガル
歌詞:マユール・プリー
振付:レモ・デスーザ
出演:プラブデーヴァー、ガネーシュ・アーチャーリヤ、ケー・ケー・メーナン、テレンス・ルイス、ローレン・ゴットリーブ、パンカジ・トリパーティー、ダルメーシュ・エーラーンデー、サルマーン・ユースフ・カーン、シャクティ・モーハン、ヌーリーン・シャー、プリンス・グプター、リヤーンシュ・シャルマー、ヴルシャーリー・チャヴァン、マーユレーシュ・ワードカル、ラーガヴ・ジュヤール、プニート・パータク、キショール・アマン、スシャーント・プジャーリー、サージャン・スィン、ラージュー・カトゥワール、サロージ・カーン(特別出演)、レモ・デスーザ(特別出演)
備考:DTスター・プロミナード・ヴァサントクンジで鑑賞。
ヴィシュヌ(プラブデーヴァー)は、ジャハーンギール・カーン(ケー・ケー・メーナン)が経営するダンス学校ジャハーンギール・ダンス・カンパニー(JDC)で振り付けをするダンサーだった。JDCのダンサーたちは、ダンスコンペティション番組「ダンス・ディル・セ(心から踊れ)」の前回チャンピオンで、第2回となる今回も優勝した。しかし、ヴィシュヌは決勝戦でJDCのダンスよりも相手のダンスの方が上だと感じており、それをジャハーンギールに話す。ジャハーンギールはテレビ番組のプロデューサーを買収したことを明かす。また、彼は外国からクリスという新しいコレオグラファーを雇い、ヴィシュヌを事務職に就かせようとする。それに反発したヴィシュヌはJDCを去る。
故郷チェンナイに戻ることを決意したヴィシュヌであったが、ダーラーヴィーに住む親友ゴーピー(ガネーシュ・アーチャーリヤ)の家に居候することになった。ヴィシュヌはダーラーヴィーに住む血気盛んな少年少女を見て、彼らにダンスを教えたいと希望する。地元政治家(パンカジ・トリパーティー)の協力を得てスタジオを手に入れたヴィシュヌは、早速彼らにダンスを教え出す。
当初は2つのライバルグループ同士のつばぜり合いのせいでなかなか練習が進まなかった。特にD(ダルメーシュ・エーラーンデー)が大きなトラブルメーカーであった。意地を張ってヴィシュヌの下でダンスを習おうとしなかったり、JDCでジャハーンギールにセクハラに遭って逃げて来たリヤー(ローレン・ゴットリーブ)の気を惹こうとしてライバルに対抗心を燃やしたりしていた。また、彼は親からダンスを習うことを止められていた。また、麻薬中毒者ながらダンスの才能を持ったチャンドゥー(プニート・パータク)も仲間に加わる。様々な試練を乗り越えながら、徐々に彼らは団結して行く。
遂に第3回ダンス・ディル・セのオーディションが始まる。ヴィシュヌのダンスチームはダーラーヴィー・ダンス・レボリューション(DDR)を名乗り、意気揚々とエントリーをする。しかし、オーディションの場でまたメンバーの不仲が表面化し、パフォーマンスは散々なものとなる。本当は落選されるべきであったが、ジャハーンギールはその失態を見て、ジョーカー役としてDDRを通させる。
その屈辱的な仕打ちに激怒したヴィシュヌは、教え子たちを厳しく叱りつける。おかげでメンバーの不仲を解消し、遂に一枚岩となる。オーディションの回を重ねるごとに視聴者の間でDDRの人気は高まって行き、遂に準決勝戦まで駒を進める。ところがここでチャンドゥーの麻薬中毒が再発する。ヴィシュヌはチャンドゥーをセンターに持って行くことで荒療治しようとし、それはかなり功を奏するのだが、準決勝戦の当日にチャンドゥーは交通事故に遭って死んでしまう。その悲しみを乗り越え、メンバーたちは追悼の踊りを踊り、とうとう決勝戦まで勝ち進む。相手は強敵JDCであった。
ここまで来るとジャハーンギールもDDRの実力を認めざるを得なかった。そこでジャハーンギールはDDRのメンバーの買収を試みる。それに乗ってしまったメンバーが出てしまった。JDCは決勝戦でDDRのダンスを丸コピーし、先にパフォーマンスをしてしまう。10分以内に振り付けをし直さなければならなくなってしまった。そこでヴィシュヌはガネーシュ・チャトゥルティー祭の踊りをフィーチャーした、型にはまらない踊りを提案する。このダンスは会場を熱狂の渦に巻き込み、ジャハーンギールですらDDRの勝ちを認める。優勝は文句なくDDRであった。
近年、ヒンディー語映画界では歌や踊りの重要度が低下している。ストーリー重視の映画作りがトレンドとなって来ており、映画全体の雰囲気に合わない場合は歌や踊りを全く入れない選択肢も定着している。もし歌が入ってもBGM程度で、踊りらしい踊りを入れることを恥じらう傾向が強い。そのような状況において、コレオグラファーの地位が低下しつつあるかもしれないことは、容易に推測できる。最近コレオグラファーから監督に転身する人が何人かいるが、それもそんな世相と関連しているのかもしれない。
「ABCD: Any Body Can Dance」は、歌と踊りを忘れつつあるヒンディー語映画界への、コレオグラファーからの逆襲だ。
コレオグラファーが監督し、コレオグラファーがダンスを踊る。もちろん振り付けはコレオグラファー。最初から最後まで、圧倒的なダンスで埋め尽くされている。やはり映画館の大スクリーンで鑑賞する群舞の迫力はすさまじい。ダンスの楽しさをダンスで表現する、そんな爽快な娯楽大作であった。
しかしながら、筋は至って単純だ。スラムの若者が裕福な人々の通うダンススクールに打ち勝つ構造、ダンスを何よりも愛するコーチの存在、ダンスよりもショーを重視するビジネスマインドの悪役、ライバル同士の確執による団結の欠如とその克服など、いわゆるスポ根モノのフォーマットにのっとった分かりやすい筋書きで、特に驚きの展開などはない。
また、ダンス中心の物語で、ダンスコンペティションをクライマックスに持って来るのは非常に陳腐に感じた。そのような構成の映画は、「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)や「Chance Pe Dance」(2010年)など、近年でもいくつか作られている。「ABCD: Any Body Can Dance」のダンスシーンでむしろ素晴らしかったのは、序盤のガネーシュ・チャトゥルティー祭シーンなど、舞台ではなく野外での踊りだ。また、「インドのマイケル・ジャクソン」の異名を持つプラブデーヴァーがソロダンスを繰り広げるディスコでのシーンも緊迫感があった。
3D技術をうまく活かし切れていたかどうかにも疑問がある。やはり3Dの映像技術は、どんなジャンルであっても、映画の面白さに大した影響は与えず、それ以外の要素――ストーリー、演技、台詞、音楽など――の方がよっぽどか重要だ。インド初の3Dダンス映画とのことだが、ただそれを言いたかっただけの映画に思えた。
プラブデーヴァーの演技力にも難があった。ダンスに関しては超一級だが、俳優としては大根で、しかもヒンディー語の台詞回しも苦手だ。一応劇中ではチェンナイ出身ということになっており、ヒンディー語が苦手な理由についても暗に説明されていたところがあるが、それでも非常に重要な役なので、彼の演技力のなさはこの映画の大きなマイナスポイントとなっていた。
それでも、ダンスの威力は圧倒的で、およそ2時間半、スクリーンに釘付けになったことには変わりがない。映画館で見てよかったと心底思わせてくれる映画である。
演技の面ではプラブデーヴァーの大根役者振りが目立つのだが、他の俳優たちは意外にまともな演技をしていた。若い俳優たちは演技に踊りに精一杯取り組んでいたし、巨漢ダンサー、ガネーシュ・アーチャーリヤも絶妙な演技をしていた。他にエンドクレジットでのダンスシーンでレモ・デスーザ監督と大御所コレオグラファーのサロージ・カーンが特別出演して踊っている。正にコレオグラファーのためにある映画だ。
音楽はサチン・ジガル。ダンス映画では音楽も重要である。その点で音楽はそこまで独創的ではなかったと感じた。ダンスシーンは多いのだが、音楽が耳に残るようなことはなかった。ARレヘマーンやシャンカル=エヘサーン=ロイなどの大物音楽監督がこの映画の音楽を担当したらもっと良くなったのではという予感もする。
「ABCD: Any Body Can Dance」は、昨今のヒンディー語映画界でコレオグラファーの地位が下がりつつある中、コレオグラファーたちによる反乱とでも呼ぶべき、とにかくダンス・ダンス・ダンスの映画。ストーリーは単純であるし、3Dの意味もあまりないと感じたが、大きなスクリーンで2時間半とにかくダンスを見続けるこの爽快感は別格だ。このようなインド映画の長所の伸ばすような実験的作品は大歓迎したい。
