
過去200年間英国の支配下にあったインドは、マハートマー・ガーンディーらの非暴力の闘争によって独立を勝ち取ったと一般に信じられている。だが、当時のインド人フリーダムファイターたちが皆、ガーンディーによって示された非暴力の道を歩んでいたわけではない。武力闘争による独立の実現を目指した者もいる。その代表格が、「ネータージー」の愛称で知られる、スバーシュチャンドラ・ボースである。
ボースは日本とも深い関わりのある人物で、日本軍の協力を得てインド国軍(INA)を率い、インパール作戦などを戦った。彼は、日本の敗戦後の1945年8月18日に、台湾の松山空港にて飛行機事故によって死亡したとされている。また、ボースの遺骨は日本に運ばれ、東京杉並区の蓮光寺に埋葬されているとされている。だが、インド人の中には、彼がその後も生存していたという説を信じる者が多く、政府もボースの死の調査をする委員会を過去に3回立ち上げている。
ボースの伝記映画としては、シャーム・ベーネーガル監督が過去に「Netaji Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero」(2005年)を撮っている。この作品は、台湾での事故までのボースの生涯を教科書的になぞっており、映画としての面白味には欠けるのだが、ボースのことを知ろうと思ったらいい素材ではある。だが、ボースの死に迫る種類の映画ではなかった。その不足を補う映画が作られた。2019年10月2日公開の「Gumnaami」である。ボースの死について調査したムカルジー委員会の調査を映画化した、実話に基づく映画である。
ボースはベンガル人であり、ボースの死についてはベンガル地方でもっとも関心が高い。「Gumnaami」はベンガル語映画界で作られており、ベンガル語映画と言えるのだが、ボースの行動範囲の広さを反映して、ベンガル語に加えて英語、ヒンディー語、そして部分的に日本語の台詞も出て来て、マルチリンガルな映画になっている。
監督はスリジト・ムカルジー。キャストは、プロセーンジト・チャタルジー、アニルバーン・バッターチャーリヤ、タヌシュリー・チャクラボルティーなど。
ボースの死については過去に、シャー・ナワーズ委員会(1956年)、コースラー委員会(1970年)、ムカルジー委員会(2005年)と、3つの委員会が設置されており、それぞれ報告書を提出している。「Gumnaami」は、ボースの伝記映画というよりも、ムカルジー委員会の報告書を巡る物語となっている。
主人公はインディア・タイムス誌の記者チャンドラチュール・ダル(アニルバーン・バッターチャーリヤ)である。上司からボースの死について取材をするように命じられ、ボースに関する文献を読み漁ったり関係者の証言を集めたりする内に、ボース生存説を信じるようになり、会社を辞め、中立的な立場からボースの死について研究し成果を発表する団体「ミッション・ネータージー」を立ち上げる。ミッション・ネータージーは実在し、チャンドラチュールのキャラクターは同団体の創立者アヌージ・ダスをモデルにしている。
チャンドラチュールの説では、ボースは台湾では死んでいなかった。第2次世界大戦の終了時、彼は連合国からお尋ね者となっており、このまま日本にいたら戦犯として逮捕される可能性があった。そこで彼は飛行機事故での死亡を演出し、自身は満州を経由してソビエト連邦に逃げていた。彼は僧侶となってチベットやネパール経由でインドに入国し、ウッタル・プラデーシュ州のラクナウーに居を定めた。彼は「グムナーミー・バーバー」や「バグワーン・ジー」などの名前で知られるようになったが、常にカーテンの向こうにおり、彼の姿を見た者は非常に限られていた。しかしながら、あらゆる証拠から、彼こそがボースであった。グムナーミーは1985年に死亡し、サラユー河で荼毘に付された。
チャンドラチュールの説は理論的にまとまっており、ムカルジー委員会も、ボースが死んだとされる台湾での飛行機事故は信憑性が低いと結論づけられた。しかしながら、その後のボースの行動や、グムナーミーの正体については、チャンドラチュールの主張が受け容れられなかった。また、政府はムカルジー委員会の承認を拒否し、こうしてチャンドラチュールの3年間に渡る努力はほとんど実らずに終わってしまった。
ボースの死自体がインド現代史における最大のミステリーのひとつであるため、その真相に迫るこの映画は、それだけで非常にエキサイティングだった。ボースの死の真相を突き止めることに一生を捧げ、妻との離婚まで経験したチャンドラチュールの情熱は、歴史的事実をなぞるだけのドライな展開になってしまいがちなこの種の作品に血肉を与えていた。しかしながら、ボースの死は未だに完全には解明されていない問題であり、この映画も様々な余地を残して終わっていた。よって、もどかしさは感じた。
なぜ、そこまでボースの死がセンシティブな問題になっているのかも、この映画を観ただけでは分かりづらいだろう。なぜインド政府はボースを1945年に死んだことにしようとするのか、そしてボースの死を否定しようとする人々が脅迫されるのか、ほとんど説明されていなかった。一般に言われているのは、インド初代首相を務めたジャワーハルラール・ネルーがボースをライバル視していたからということだ。ネルーもボースもエリートだったが、国家公務員試験である帝国文官試験(ICS)に合格したボースは、エリート中のエリートであった。事実、頭脳明晰さで見たら、ボースは頭一つ抜き出た才人であった。しかも、彼が主導した反英武力闘争を支持するインド人は多く、もし独立インドに彼が現れたら、初代首相としてネルーよりもボースの方が推される可能性もあった。そもそも、ボースがいれば、印パ分離独立も起きなかったと信じられている。それほどカリスマ性のある政治家だったボースが、独立からしばらく経った後でも、インドに戻って来たとなると、政局になる怖れがあった。よって、当時の国民会議派の政治家たちは、ボースの存在を怖れたのである。
ムカルジー委員会が設立されたのは、国民会議派のライバル政党であるインド人民党(BJP)が中央政府の与党となっていた時期だった。しかしながら、2004年に政権交代があり、国民会議派が与党となった。ムカルジー委員会の報告書が完成したのが2005年で、翌年に国会に提出された。国民会議派の政治家たちは、ジャワーハルラール・ネルー、インディラー・ガーンディー、ラージーヴ・ガーンディー、そしてソニア・ガーンディーと連なる、いわゆるネルー・ガーンディー王朝の血統主義を何より重視しており、ボースの死に関して不都合な真実が明らかになると、ネルーに批判が集まり、自動的に党のリーダーシップの問題に発展してしまう。そういうこともあって、ムカルジー委員会の報告書は無視されたのであろう。
スリジト・ムカルジー監督は、ボースが1945年以降も生存していたという説に肩入れをした作り方をしているため、「Gumnaami」を一通り観ると、やはりボースは生きていたと信じたくなる。それ以外にも様々な事実にスポットライトが当てられているが、個人的に一番驚いたのが、インドを代表するラム酒オールド・モンクの名称についてのトリビアである。モーハン・ミーキン社が製造・販売するオールド・モンクの名称は「老僧」という意味だが、なんとこれはグムナーミー・バーバーのことらしい。1954年にオールド・モンクのブランドを立ち上げたヴェード・ラタン・モーハン社長はグムナーミー・バーバーと交流があったようで、彼をイメージして付けたのがこの名称のようだ。ただし、オールド・モンクのラベルに描かれている顔は、どう見てもインド人には見えない。眉唾なのではないかと思うが、もし事実だったら面白い。
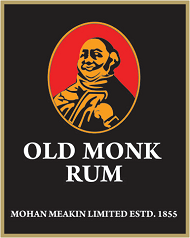
ちなみに、モーハン・ミーキン社は元々、1855年にスコットランド人エドワード・アブラハム・ダイヤーによって創立された会社だが、その息子のレジナルド・ダイヤーは、1919年のジャリヤーンワーラーバーグ虐殺事件を主導した人物である。ジャリヤーンワーラーバーグ事件は、その後の反英闘争に決定的な影響を与えた事件であった。そう考えると、オールド・モンクはインド現代史の重要事件と重要人物に関わりをもった酒ということになる。
「Gumnaami」は、インド現代史の最大のミステリーのひとつ、ネータージー・スバーシュチャンドラ・ボースの死の真相に迫った映画である。映画そのものが面白いと言うよりも、ボースの死を巡る謎が面白過ぎて、その展開に釘付けになる。最終的に明確な結論は出されていないが、一通り観ると、「ボース=グムナーミー・バーバー」説を信じたくなってしまう。ボースのことを知りたかったら、シャーム・ベーネーガル監督の伝記映画「Netaji Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero」と併せて鑑賞することをお勧めする。
